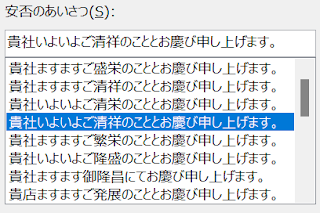iPhoneでサウンドを利用するというと、着信音とかApple Musicとかになるかと思いますが、その他にいくつかサウンドに関する面白い機能があります。
その一つが「バックグラウンドサウンド」で、iPhoneを用いて海のさざ波や雨だれの音などの環境音・ノイズを発生させるという機能です。
人によってはBGMをかけるよりも落ち着くという事もあるでしょうし、結構使える機能なのでは?
「バックグラウンドサウンド」をオンにすると「サウンド」の項目で選ばれている環境音・ノイズが流れ始めます。
音量設定やオーディオプレイヤーやゲームアプリの音に重ねて鳴らすかや、スリープ状態でも音だけは鳴らすのかなど細かな設定も可能です。ただ、これだと毎回「設定」を開いて再生しないといけなくて、面倒ですので、バックグラウンドサウンドの設定後に、「コントロールセンター」で一発起動出来るようにしておきます。
ちなみにコントロールセンターは画面下からスワイプ操作すると表示される画面で、画面の明るさや音量設定など各種機能に簡単にアクセスできる便利機能です。
コントロールセンター表示後に、左上の「+」マークをタップすると画面下部に「コントロールを追加」の表示が出るので、それをさらにタップします。
様々なボタンの表示が出ますが、下の方にスワイプして「聴覚アクセシビリティ」という項目の「バックグラウンドサウンド」のボタンをタップします。
コントロールセンターにボタンが追加されるので、任意の場所にドラッグして移動させます。
追加後、ボタンを押すとサウンドが流れ、再度押すと止まるようになります。
確認してみると機内モード、つまりオフライン状態でも再生は可能ですので、データ通信も気にする必要はなさそうです。
ご興味のある方は是非お試しください。